こんにちは、はやぶさと申します。
会社員17年が過ぎ、このまま人生進むのも面白くないと思いスキルアップ目的でブログを始めてみました。
今回のテーマは”話す”です。
私は話すことは好きですが苦手です。特に人前では…そう、口下手なんです。
ビジネスの中で特に人前で話さなければならない一人の時間になるととても緊張します。
- 話したいことをうまくまとめられない
- ちゃんと話が伝わっているのか、理解してもらえているのか不安
- 話し方に余裕がない
- 緊張して相手の顔まで見る余裕がない
などなど、今まで発表の場で「うまく話せたな〜」と思えたことはほとんどありません。
30代後半にもなると色々立場や環境も変わり、話し方も成長させなければと考えるわけです。
そんな時に目についた書籍が、「頭のいい人が話す前に考えていること」です。
ビジネス書ランキングの中でも上位で、今一番売れているコミュニケーション本に惹かれました。
なぜこの書籍を読もうと思ったかというと、
- 頭のいい人はどういう考え方、視点で話をしているのか
- 私と頭のいい人は、話す前の考え方は何が違うのか
- 考え方を変えると話し方を変えることができるのか
他の人がどのようなことを考えているのか参考にして、人前で話すことの苦手意識が軽減できればと思い読んでみました。
頭のいい人の考え方、思考の深め方をポイントをまとめてみます。

本の構成は、第一部「頭のいい人が話す前に考えていること」、第二部「一気に頭が良くなる思考の深め方」の二部構成になっています。
第一部 頭のいい人が話す前に考えていること
こちらでは「知性」と「信頼」を同時にもたらす7つの黄金法則を紹介しています。
〈黄金法則その1〉 とにかく反応するな
◆「怒っているとき」は、頭が悪くなる。
頭のいい人は、”キレること””感情的になること”でどれだけ大きな損失を被るかを知っている。
感情的になった時もすぐに反応するのではなく、感情をコントロールし、冷静になって考える方がメリットがある。感情的な発言で後悔することもあるので注意。
”話す前にちゃんと考える”ということは、感情に任せて反応するのではなく、”冷静になること”が大事。
〈黄金法則その2〉 頭のよさは、他者が決める
学力など頭のよさを計る要素はいくつかあるが、頭のよさを決めるのは、他者である。
周りから”頭がよい”と認識され、認識している人が多ければ多いほど、その人は”頭がいい人”となる。
頭のいい人の思考の深め方は、常に”相手が何を求めているのか?”を考えながら生活すること。自分のアイデアが受け入れてもらえない人は、その視点で生活できていない場合がある。
〈黄金法則その3〉 人はちゃんと考えてくれてる人を信頼する
頭のいい人は賢いふりをしない、賢い振る舞いをする。
会議では最初に発言することが重要。最初の発言は勇気がいるし、勉強もしなければいけないが、こういう行動が賢い振る舞いとなり評価が高い。
一方で、賢いふりは「なんか言っているようで何も言ってない発言」をする人たちのこと。
優秀なだけではなく、長期的な人間関係を築くには“信頼”が必要である。
プライベートでもビジネスでも“ちゃんと考えてくれている”という心情になったとき信頼関係が生まれ、相手の心を動かすタイミングである。
〈黄金法則その4〉 人と闘うな、課題と闘え
頭のいい人は論破することはせず、議論の奥にある本質的な部分を見極めようとする。
ちゃんと考えて話すということは、相手の言っていることから、その奥に潜む想いを想像して話すということである。
クレーム対応が上手い人の特徴は、できないものはできないと言いくるめるのではなく、相手が何を想ってクレームを言っているのか、根底にある想いの部分にたどり着くことができる人のことである。
〈黄金法則その5〉 伝わらないのは、話し方ではなく、考えが足りないせい
オシャレな言い回しや頭の良さそうな話し方を一生懸命勉強しても、結局は伝わらない、心が動かないことがよく起こる。うまい話し方の型にはめて話すことは、賢い振りであり頭のいい人には見破られてしまう。
“自分の考えの欠点に気づく”ことで思考を深めることができる。そして相手に伝わらなければ、考えが足りなかったと考える。これは頭のいい人のマインドであり思考の質を高めるポイント。
〈黄金法則その6〉 知識は誰かのために使って初めて知性となる
頭のいい人は“賢いふり”ではなく“知らないふり”をすることがポイント。
ここでは相手に簡単にアドバイスするのではなく、聞くことに徹し相手に話してもらうことで、自ら解決にたどり着く事例を紹介している。
知識を披露するだけでは知性を感じられないので注意。知識を披露することで本当に相手のためになっているか考える。相手のためになった瞬間に知性が溢れてくる。
〈黄金法則その7〉 承認欲求を満たす側に回れ
“話が上手になること”よりも大事なこと、それは“承認欲求をどうコントロールするか“である。
知識を披露したくなることも承認欲求の一つであるが、裏を返すと承認欲求をコントロールできれば、知識披露を抑えることができる。
承認欲求をコントロールし、コミュニケーションの強者になるには
①自信を持つこと ②口ではなく、結果で自分自身の有能さを示すこと
相手の承認欲求を満たす方法は、”結果を出した上で親切にする”ことである。そうすることで絶対的な信頼を得られる。
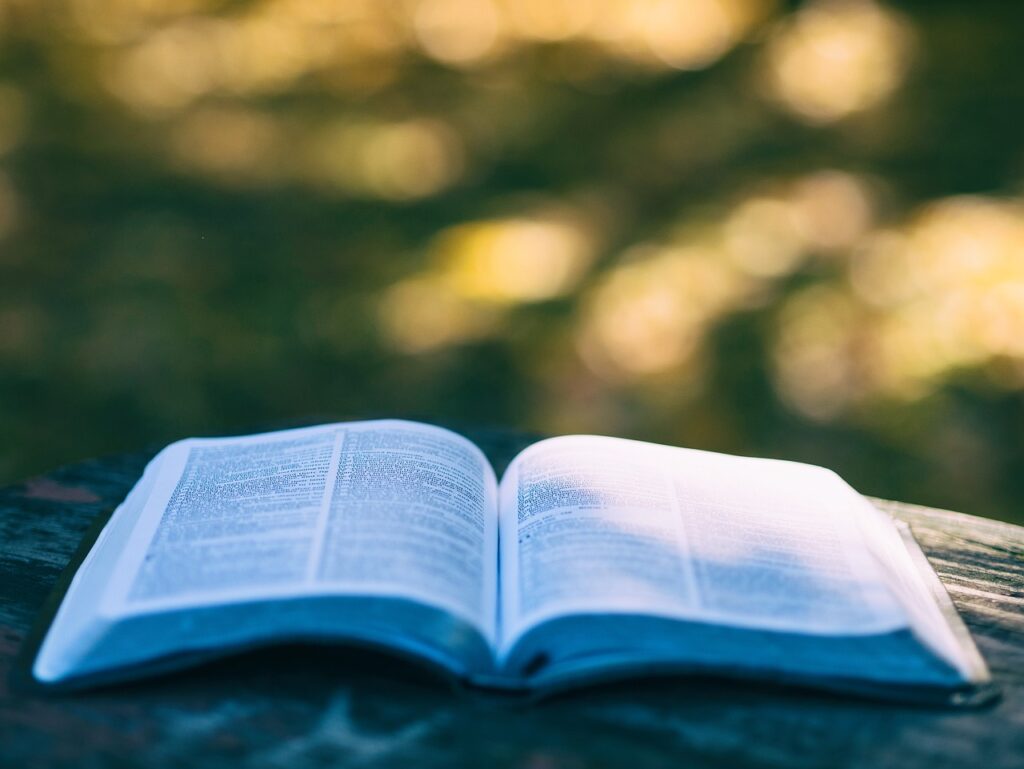
第二部 一気に頭のいい人になる思考の深め方
「知性」と「信頼」を同時にもたらす5つの思考法
その1 「客観視」の思考法
◾️話が浅い人の特徴
・根拠が薄い
「少量の、根拠の薄い情報」で話すということは、本人はあたかも考えて話をしている気になっているが、実は話の内容が浅く見られてしまう。
①自分の意見と真逆の意見を調べる ②統計データを調べる ことが話を深くするコツ。
頭のいい人の正確なデータの調べ方は出所を気にして調べている。
・言葉の「意味・定義」をよく考えずに使う
人によって言葉の定義にズレがあり、それが元でトラブルに発展することもある。この言葉を使うことで相手がどのように理解するかまで考えて話せる人が頭のいい人。
・成り立ちを知らない
成り立ちを知ることで人と違うアイデアも深い議論も生まれる。
成り立ちを調べるコツは、語源を調べ次に広まった地域や場所を調べること。
その2 「整理」の思考法
◾️考えるとは整理することである
・結論から話す
結論の定義とは「相手が最も聞きたいであろう話」のことである。
結論から話すことは、相手に聞く準備をさせるための行為。
・「事実」と「意見」を分ける
事実と意見を混同することは注意。
意見なのに、事実のように話す人は、思い込みの強い人と見られてしまう。
事実と意見を分けて話すコツは
それは証明可能な事実か?
自ら判断を下した意見か?
反射的に回答するのではなく、一息おいて考えてから回答すること。
「事実を求められているときに、意見を述べない」「意見を事実のように言わない」
ということを意識しながら、自分の意見を持つようにする。
その3 「傾聴」の思考法
頭のいい人は、相手の話を正確に理解しようと、相手の言いたいことを考えながら聞く。
・知的で慕われている人の態度
- 肯定も否定もしない
- 相手を評価しない
- 意見を安易に言わない
- 話が途切れたら、むしろ沈黙する
- 自分の好奇心を総動員する
・アドバイスするな、交通整理せよ
相手の話から余分な情報を捨てて、判断に必要な情報だけを残してあげる行為。
・整理しながら聞く技術
- ゴールの確認
- 考えていることを聞く
- 話を整理して相手の意思決定を助ける
アドバイスしたい時ほど、相手の話を整理しながら正確に聞くことがポイント。
その4 「質問」の思考法
◾️グーグルが使う質問術
プライベートでも有効な万能な質問術で、相手の話を引き出したいときに効果的。
- “過去に行った行動”についての質問
「直面した状況にどのように対応したか?」 - ”仮定の状況判断”に対する質問
「仮に〜このような状況に置かれたとしたら、どのようにしますか?」 - ”状況(シチュエーション)”に関する質問
「その時どのような状況でしたか?」 - ”行動(アクション)”に関する質問
「そのとき、何をしましたか?」 - ”成果”に関する質問
「行動の結果、どのような変化がありましたか?」「何か現場で反発はありましたか?」
質問の”質”は、質問をする前にどれだけ仮説を立てられるかで決まる。
「もし仮に私が〇〇の立場だったら・・・」と仮説を立ててから質問することで、ストレートに質問するよりも相手の思いを引き出せることがある。
◾️「教わる技術」質問がうまい人と下手な人の違い
教わり上手な人の質問の仕方
- 一度にひとつのことしか聞かない(質問を畳み掛けない)
- 目的を知らせる(ざっくりした質問は相手を困らせる)
- 要素分解して具体的に聞く(聞きたいことを分解し整理する)
- 今までにやったことを細大もらさず伝える(過程を伝えることで相手も答えやすくなる)
教わるのがうまい人は、聞きやすい人や身近な人ではなく、”聞くべき人”を考えてから聞きに行き、さっさと課題を解決し成長していく。
その5 「言語化」の思考法
他人とコミュニケーションを取ると、”コミュニケーションコスト”というものが発生する。
これは「言語化する」というコミュニケーションにおいて一番労力のかかることを、相手にも負担してもらうということ。このコミュニケーションコストは基本話し手が支払うものである。
言語化のコストを相手に払ってもらっているうちは頭がいいと認識されない。言語化のコストを進んで支払う側に回ることが大事。
ちなみに、頭のいい人は電話を嫌う。なぜなら半強制的に、コミュニケーションコストを支払わなければならないからだ。
◾️言語化の質はアウトプットの質を決める。
ここでの言語化はアウトプット全般のことを指しており、言葉にするだけではなく、建築家やデザイナーなど形で表現することも含まれている。
- 思考の質は、言語化の質を決めます
- 言語化の質は、アウトプットの質を決めます
- アウトプットの質が高ければ、人の心を動かします
- 人の心を動かせば、行動につながります
ちゃんと考えることを突き詰めれば、人を動かすアウトプットを生み出すということ。
◾️言語化の質を高めるたった一つの型は、再定義すること。
〇〇ではなく、△△である。
再定義していくと、新しい発見、コンセプトが浮かんでくる。
◾️言語化は挨拶と同じ、習慣化することで言語化能力を強化することができる。
言語化の習慣
- ネーミングにとことんこだわる・・・名前をつけることは言語化能力が最も必要
- 「ヤバい」「エモい」「スゴい」を明日から使わない・・・簡単な言葉ではなく語彙力を高める
- 「読書ノート」「ノウハウメモ」を作る・・・語彙を増やすために有効なものが読書
まとめ
最初に話すことを苦手としている理由を書いていますが、私の中では「カッコよく話そう」や「頭が良さそうに話そう」と意識するあまりに自滅していることに気付かされました。
「黄金法則2 頭のよさは、他人が決める」は私の考えをひっくり返してもらえた言葉でした。
相手が決めてくれるから、そんなにプレッシャーを感じる必要はないんだと…少し気持ちが楽になったように感じます。
この一冊を通じて考え方や思考の深め方を様々な視点で説明していますが、どの部分を見ても、”他者”に対してフォーカスした内容になっています。
”他者”の気持ちを考えられる人が頭のいい人であり、普段から「この人頭いいな」と感じる人は、相手の立場に立って物事を考え、話ができているのだと思います。
知識量、経験値のような学力も頭のよさになりますが、最終的に頭のよさを判断するのは相手ということがポイントです。
最後に著者は”本当に頭のいい人とは、大切な人を大切にできる人”と話されています。
私と関わる方を大切にする意識を持って生活していきたいと思います。
7つの黄金法則、5つの思考法を実践しながら、少しずつ頭のいい人に近づけるように努力していきましょう。



コメント